昨今「専守防衛」という言葉を政府が主張しているのを聞くのではないでしょうか?
また、専守防衛とは具体的にどういう意味なのでしょうか?
そのような「専守防衛」という考え方が抱える問題点についても分かりやすく解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
「専守防衛」とはどういう意味なのか
専守防衛とは、日本独自の防衛戦略の基本姿勢を指します。
内容は、「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その防衛力行使の態様も、自衛のための必要最低限度にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最低限度のものに限られる」とされています。
このように、「専守防衛」とは、憲法精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいいます。
また、政府としても、防衛の基本的な方針である「専守防衛」を維持することは変わらない、としています。
「専守防衛」の問題点とは
専守防衛とは、相手国から攻撃されたとき初めて日本が防御力を行使でき、整備する防御力は自衛のための必要最低限度にとどめるというものです。
これにこだわることで、有事の際、自衛隊員や国民の犠牲をいたずらに増やしてしまうおそれがあります。
また、相手からすると、専守防衛を掲げる日本を低リスクで攻撃できるといえるでしょう。
それは、原則的に日本の自衛隊から攻撃を受けることはないからです。
ロシアのウクライナ侵攻も踏まえると、消極的な安全保障政策である専守防衛の意義が問われることになる可能性があります。
「専守防衛」から「積極防衛」へシフトすることで、より安全を保障できる可能性すらあるからです。
いずれにせよ、米国をはじめとした他国と連携し、防衛計画を精査する必要があるります。
「専守防衛」と憲法9条の関係とは
憲法第9条には戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定が置かれています。
ですが、わが国は独立国である以上、主権国家としての自衛権を否定するわけではありません。
したがって、自衛のための必要最低限度の実力を保持することは、憲法上認められていると、政府は解しています。
以上より、憲法に基づいて自衛権を行使するため、わが国では「専守防衛」という姿勢をとっています。
まとめ
以上で、専守防衛について、また、専守防衛の問題点や憲法9条との関連について解説してきました。
ロシアによるウクライナ侵攻が進む中、日本の防衛の在り方が問われるようになりました。
そのため、専守防衛という我が国の防衛姿勢はしっかりと知っておくべきでしょう。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

現在は大手IT企業でSEとして働きながら、本サイトを運営しております。アニメ視聴歴は10年以上で、ゲームもこれまで様々なものをプレイしてきました。これまでの自身の経験を活かしながら、本サイトにて有益な情報を届けることが出来るように心がけています。

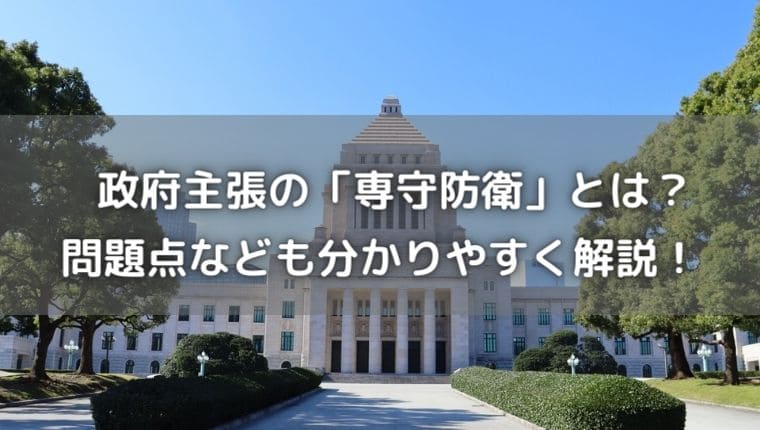


コメント